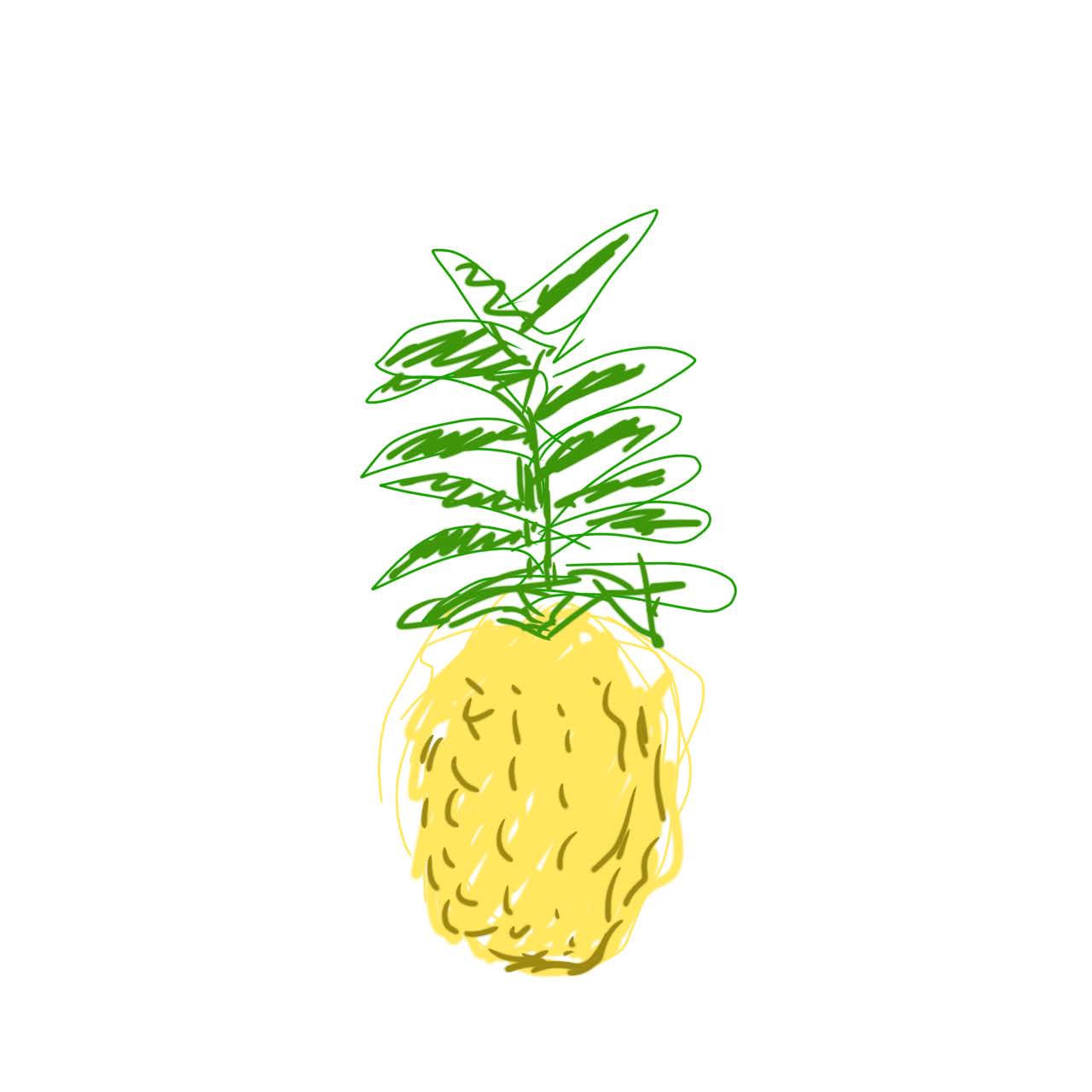彼は死んだ。
私と一緒に生きていくと信じていた。
しかし、いつの間にかいなくなっていた。
私が病を患い、病床で横になっていたとき、枕の上で首を傾けたときにはもうそこにいなかった。
頭痛がひどい。
後頭部から前頭部にかけてミシミシと音を立てるように何かを詰め込まれているような痛さ。
全身が怠い。
体のどこにも力が入らず、ふと起き上がろうとすると体の奥底から詰まったトイレのように口元に何かが沸き上がってくる。
日頃の行いだろうか。
彼には紳士に向き合うことを念頭に置いていた。
将来を夢見ていた。
幸せな家庭を築き、子供を2人産み、一緒に育てていくんだと、そう信じきっていた。
でも私は彼を殺した。
彼は狭いキッチンで憂鬱そうに朝食を作っていた。私は襖を少し開き、それを視界に入れた。彼は振り返った。私は視線を遮るようにそっと襖を閉めた。
帰る意思はもう昨晩に決めていた。
彼とは相容れないのだと確信したから。少し迷ったりもしたが、ここで一緒に気まずい空気を吸って錆びていくより、互いのためにも帰ったほうが懸命だと思ったのだ。
私は後悔した。こんなことになるなら付き合うんじゃなかったと。そして、別れるんじゃなかったと。
彼はいい人だった。そう、ただいい人だった。
私が失敗しても最後は許してくれるし、世間の言う悪い習慣というのを持ち合わせていなかった。
いい人だった。私には勿体ない人だった。だから何度も自問自答した。彼にはもっと相応しい人がいる。そして、彼もそう思っている。
「私と付き合ってて楽しい?私のこと好き?」つい、そう聞いてしまった。答えはとっくに分かっていたのに。彼は嘘をつかない。私が求める優しい嘘も、言ってはくれない。
「大切だとは、思っているよ。」
分かっていたのに、ひどく傷付いた。もうあの頃の快楽は得られない、戻れない、ここはどこ?
徐々に心が廃墟のように、廃れていった。
彼をもう愛せなくなってしまっていた。
乱暴に襖を開いた。
「朝ごはん、食べる?」
「要らない」
彼は空虚な言葉で朝食を誘った。キッチンの端では、銀のボウルにキャベツとキュウリがぐちゃぐちゃになって詰め込まれていた。とても不味そうだった。
心なしか足取りも重くなり、空気の重さを感じるのに空気が無いかのように、足音が部屋に響いた。
彼との思い出を詰め込みすぎた重たい鞄を持ち上げ玄関を開けた。
「気を付けてね。」
彼の言葉に恐怖を覚え、ドアを思い切り閉めた。
私は彼を殺した。
そうだ、彼はここで死んだのだ。